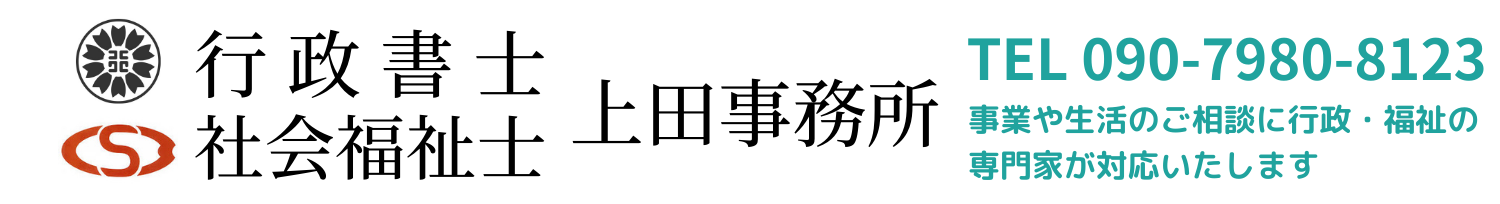社会福祉法人は、その主たる事業である社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて「公益事業」や「収益事業」を行うことができます。
(公益事業及び収益事業)
昭和二十六年法律第四十五号
第二十六条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
2 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
社会福祉法
この記事では「公益事業」について説明します。
広告
公益事業とは
社会福祉法人の公益事業とは、次の条件に該当する事業をいいます。
①公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。
②その事業を行うことにより、社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
③その事業は、社会福祉事業に対し、従たる地位にあること。
④社会福祉と関係があること。
⑤公益事業に剰余金を生じたときは、その法人が行う社会福祉事業や公益事業に充てること。
公益事業の例
社会福祉法人が行う公益性のある事業について、どのような事業が公益事業にあたるかは、厚生労働省が「社会福祉法人審査基準」や「社会福祉法人審査要領」に具体例を示しています。
「社会福祉法人審査基準」が例示する公益事業
厚生労働省が「社会福祉法人審査基準」に例示している公益事業は次のとおりです。
(社会福祉事業として行うものは除きます)
①必要な者に対して、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
②必要な者に対して、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文
化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という)を支援する事業
③入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対して、住居を提供または確保する事業
④日常生活を営むのに支障がある状態の軽減または悪化の防止に関する事業
⑤入所施設からの退院・退所を支援する事業
⑥子育て支援に関する事業
⑦福祉用具、その他の用具・機器、住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
⑧ボランティアの育成に関する事業
⑨社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業
(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
⑩社会福祉に関する調査研究等
「社会福祉法人審査要領」が例示する公益事業
厚生労働省が「社会福祉法人審査要領」に例示している公益事業は次のとおりです。
(社会福祉事業として行うものは除きます)
事業規模が小さいもの
⑪社会福祉法第2条第4項第4号に掲げる事業
その事業内容が、第1種社会福祉事業や、第2種社会福祉事業のうちの一部のものに該当するものの、いわゆる「事業規模要件」を満たさないため(事業として小さすぎるため)に、社会福祉事業に含まれない事業です。
(定義)
昭和二十六年法律第四十五号
第2条(略)
4 この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
一 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
二 実施期間が六月(前項第十三号に掲げる事業にあつては、三月)を超えない事業
三 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
四 第二項各号及び前項第一号から第九号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては五人、その他のものにあつては二十人(政令で定めるものにあつては、十人)に満たないもの
(以下略)
社会福祉法
上記の「第二項各号及び前項第一号から第九号までに掲げる事業」は次のとおりです。
(定義)
昭和二十六年法律第四十五号
第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
六 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
七 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
一の二 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
二 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
二の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
二の三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)に規定する養子縁組あつせん事業
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
四の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
六 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
七 削除
八 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
九 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
(略)
社会福祉法
また、上記の「社会福祉法第2条第4項第4号」の条文中、事業規模要件について「政令で定めるものにあつては、十人」とあります。
政令とは、社会福祉法の細かい部分を決めるルールである「社会福祉法施行令」のことです。
次のとおり定めています。
(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
昭和三十三年政令第百八十五号
第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)のうち厚生労働省令で定めるもの
社会福祉法施行令
上記の条文中、障害福祉サービス事業については「厚生労働省令」で、さらに細かく決めています。
厚生労働省令とは、社会福祉法のさらに細かい部分を決めるルールである「社会福祉法施行規則」のことです。次のとおり定めています。
(令第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業)
昭和二十六年厚生省令第二十八号
第一条 社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号。以下「令」という。)第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一項第一号に規定する就労継続支援A型に係る障害福祉サービス事業
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援(前号に掲げるものを除く。)(以下「生活介護等」と総称する。)に係る障害福祉サービス事業であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十七条(同令第五十五条、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。)及び第五十七条第一項並びに第八十九条第二項の離島その他の地域であつて厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて実施されるもの
社会福祉法施行規則
以上のとおり、社会福祉法に定める社会福祉事業に該当するサービスであっても、その事業規模によって、社会福祉事業に該当したり、公益事業に該当したりするので、法人において新しいサービスを始める場合や、事業規模を縮小する場合などには、注意が必要です。
介護保険法のサービス
⑫介護保険法に規定する次の事業
・居宅サービス事業
・地域密着型サービス事業
・介護予防サービス事業
・地域密着型介護予防サービス事業
・居宅介護支援事業
・介護予防支援事業
・介護老人保健施設を経営する事業
・地域支援事業を市町村から受託して実施する事業
・老人保健法に規定する指定老人訪問看護を行う事業
※居宅介護支援事業等を、特別養護老人ホーム等の社会福祉事業の施設の経営に付随して行う場合や、小規模で社会福祉事業と一体的に行われる事業または社会福祉事業の施設の機能を活用して行う事業の場合には、定款上、公益事業として記載しなくとも差し支えありません。
その他の公益事業
⑬有料老人ホームを経営する事業
⑭社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
⑮公益的事業を行う団体に、事務所・集会所等として、無償または実費に近い対価で使用させるために、会館等を経営する事業
※営利を行う者に対して、無償または実費に近い対価で使用させるような計画は適当ではないとされます。また、このような者に対して収益を得る目的で貸与する場合は、収益事業となります。
地域公益事業について
社会福祉法人は、社会福祉事業や公益事業において、日常生活・社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料または低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないとされています。
(経営の原則等)
昭和二十六年法律第四十五号
第二十四条(略)
2 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。
社会福祉法
この福祉サービスを「地域における公益的な取組」といいます。
この「地域における公益的な取組」のうち、公益事業によるものを「地域公益事業」といいます。
社会環境の変化に伴い、福祉ニーズが多様化・複雑化していく中で、既存の社会福祉事業では十分に対応できない福祉ニーズに対して、社会福祉法人が独自の創意工夫によって対応することが期待されています。
「地域における公益的な取組」について、厚生労働省が公表した「好事例集」から、その一部について、概要を紹介します。
・子育て中の親へのカウンセリングの実施
・引きこもり状態の方への相談支援、社会とのつながりを構築するためのサポート
・引きこもり状態の方への就労・外出支援
・引きこもり状態の方へ、居場所としてZoomで夜カフェを実施
・生活困窮者等の住まい探しの支援、内覧・物件契約の同行、入居後のサポート
・生活困窮者等に対するゴミ出し、掃除、買い物代行、買い物サロン(移動スーパー)の実施
・知的障害や生きづらさを抱える方に、スポーツや料理教室など、余暇活動の機会を提供
・困窮家庭の小中学生等に、子ども食堂などの居場所づくり
・生活困窮者や孤食の方ほか、地域住民全体に対して、交流食堂を実施
・家から出にくい方や福祉事務所の利用者に、月1回カレーライスを提供
・発達障害またはその疑いのある小中学生に対する学習支援
・ひとり親世帯や難民等の子どもに対して学習塾と食事支援を実施
・独居や交通手段がない方などのための買い物サロン(自動車を提供しての集団での買い出し)
・社会交流ができない高齢者や過疎地域の高齢者向けの見守り活動、縁側訪問、声かけ
・生活困窮者に対する現物支給(生活消耗品、衣類)と調理器具の貸与
・生活困窮者やひとり親家庭へのフードバンクの実施
・住居が無い生活困窮者に対して、職員宿舎の空き部屋を、一時的な宿泊場所として提供
・生活困窮者や高齢者に対して、スマホ教室を実施
・町内の児童に、朝ごはんや調理の大切さを伝える、子ども塾を開催
こうした「地域における公益的な取組」について、公益事業(地域公益事業)として実施する場合、社会福祉充実残額を保有する社会福祉法人は、社会福祉充実計画を策定し、他の公益事業よりも地域公益事業の実施に優先的に再投資することが求められています。
(社会福祉充実計画の承認)
昭和二十六年法律第四十五号
第五十五条の二(略)
4 社会福祉法人は、前項第一号に掲げる事項の記載に当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事業の順にその実施について検討し、行う事業を記載しなければならない。
一 社会福祉事業又は公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業に限る。)
二 公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業を除き、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものに限る。第六項及び第九項第三号において「地域公益事業」という。)
三 公益事業(前二号に掲げる事業を除く。)
(略)
社会福祉法
また、社会福祉法人は、地域公益事業を行う計画の策定にあたっては「地域公益事業の内容及び事業区域における需要」について「住民その他の関係者」の意見を聴かなければならないこととされています。
第五十五条の二(略)
昭和二十六年法律第四十五号
6 社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たつては、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。
(以下略)
社会福祉法
この「当該事業区域の住民その他の関係者の意見」を聴く場を「地域協議会」といいます。
つまり、社会福祉法人が、地域公益事業を行うにあたっては、その計画段階で、事業の実施を予定する地域に設置された地域協議会の意見を聴くことになります。
まとめ
社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、「公益事業」を行うことができます。
社会福祉法人の公益事業とは、次の条件に該当する事業をいいます。
①公益を目的とする事業で、社会福祉事業以外のもの
②社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがない
③社会福祉事業に対し、従たる地位にある
④社会福祉と関係がある
⑤公益事業に生じた剰余金は、その法人が行う社会福祉事業や公益事業に充てる
公益事業に該当する事業には、介護保険法上の各種サービスや、有料老人ホームの経営など、様々なものが含まれます。
第1種社会福祉事業や、第2種社会福祉事業のうちの一部のものに該当するものの、いわゆる「事業規模要件」を満たさないために、社会福祉事業に含まれない事業も含まれます。
社会福祉法人が、公益事業によって、日常生活・社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料または低額な料金で福祉サービスを提供する場合、これを「地域公益事業」といいます。
広告