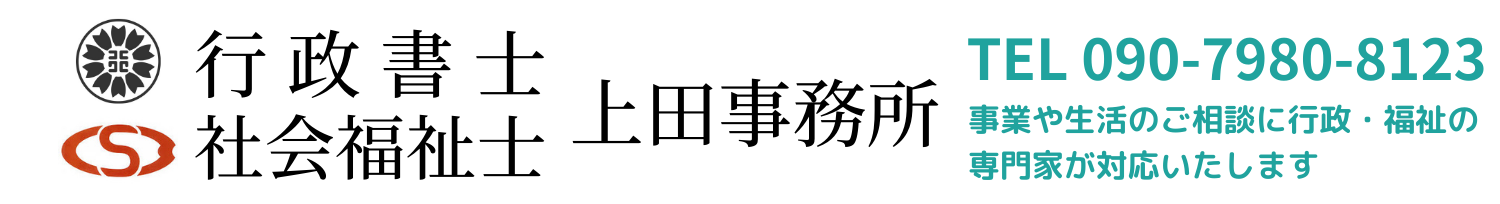産業廃棄物収集運搬業許可とは
廃棄物の収集運搬業者が、産業廃棄物の収集運搬を受託するためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
この点、運搬車両から産業廃棄物を下ろさずに、排出場所から処分地などへ直送する場合と、いったん保管場所へ集積する場合とで、それぞれ個別の許可が必要になります。
ここでは、排出場所から処分地などへ直送する場合に必要となる「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)」の許可について、その取得条件をみていきます。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可の種類
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可は、収集運搬する廃棄物の種類に応じて、さらに2種類に分けられ、それぞれについて個別の許可が必要になります。
廃棄物の種類は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、下表のとおり区分されています。
| 廃棄物の区分 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる物 |
|---|---|
| 産業廃棄物 | 事業活動で発生したもののうち、法令で定めた20種類 |
| 特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの |
| 一般廃棄物 | 産業廃棄物以外のもの |
| 事業系一般廃棄物 | 事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの |
| 家庭廃棄物 | 一般家庭の日常生活から発生したもの |
| 特別管理一般廃棄物 | 一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの |
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)は、上表のうち「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」との収集運搬にあてはまるので、それらを運搬収集するにあたって、個別に許可が必要になります。
産業廃棄物
上表の「産業廃棄物」については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律やその施行令で、さらに細かく定められており、おおむね下表のとおりです。
下表の「排出限定業種」とは、その欄に記載のある業種が、その左に記載の種類の廃棄物を排出した場合に限り、その廃棄物を産業廃棄物として扱うという意味で、業種限定の産業廃棄物です。
| 種 類 | 排出限定業種 | 内容(事業活動に伴うものに限る) |
| 燃え殻 | 石炭がら、焼却残さ、炉清掃廃棄物等 | |
| 汚泥 | 泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの | |
| 廃油 | 揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、すべての廃油 | |
| 廃酸 | 酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの | |
| 廃アルカリ | アルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの | |
| 廃プラスチック類 | 固形状の廃プラスチック類 | |
| 紙くず | 建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 | 左記の業種から発生する紙くず (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くずを含む) ※合成紙は廃プラスチック類 |
| 木くず | 建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 | 左記の業種から発生する木くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くずを含む) |
| 繊維くず | 建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) | 左記の業種から発生する天然繊維くず、糸くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物を含む) ※合成繊維くずは、廃プラスチック類 |
| 動植物性残さ | 食料品製造業、飲料・飼料製造業(たばこ製造業を除く)、医薬品製造業、香料製造業 | 左記の業種において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 ※飲食店等から排出される動植物性残さは一般廃棄物 |
| 動物系固形不要物 | と畜場 食鳥処理場 | とさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
| ゴムくず | 天然ゴムくず ※合成ゴムは、廃プラスチック類 | |
| 金属くず | 鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かす等 | |
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 1 ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず等 2 コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくず等 3 陶磁器くず:土器くず、陶器くず等 | |
| 鉱さい | 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)等 | |
| がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物 | |
| 動物のふん尿 | 畜産農業 | 畜産農業から発生する家畜のふん尿 |
| 動物の死体 | 畜産農業 | 畜産農業から発生する家畜の死体 |
| ばいじん | ばい煙発生施設や焼却施設等において、集じん施設によって集められたもの等 | |
| 処分するために処理したもの | 産業廃棄物を処分するために処理したもの |
特別管理産業廃棄物
上表の「特別管理産業廃棄物」については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律やその施行令で、さらに細かく定められており、おおむね下表のとおりです。
| 種 類 | 排出限定業種 | 内容(事業活動に伴うものに限る) | |
| 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の廃油 | ||
| 廃酸 | pH2.0以下(著しい腐食性のあるもの) | ||
| 廃アルカリ | pH12.5以上(著しい腐食性のあるもの) | ||
| 感染性産業廃棄物 | 医療関係機関(病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設等) | 血液等、血液等が付着した鋭利なもの、病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたもの、その他血液等が付着したもの、汚染物が付着した廃プラスチック類など。 | |
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | |
| PCB 汚染物 | PCBが塗布され又は染み込んだもの PCBが付着又は封入されたもの | ||
| 廃水銀等 | 施行規則別表第1に掲げる施設において生じたもの | 廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く) 例:金属水銀、水銀化合物の試薬、ポロシメーター(水銀部分) | |
| 鉱さい | 環境省令で定める基準を超えているもの | ||
| 廃石綿等 | 石綿建材除去事業 | 吹付け石綿除去物等 | |
| 大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉じん発生施設及び当該施設が設置されている事業場 | 集じん施設によって集められたもの、石綿等付着物(防じんマスク、集じんフィルター等) | ||
| ばいじん 燃え殻 | 大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設等に掲げる廃棄物焼却炉において生じたもの | 環境省令で定める基準を超えているもの | |
| 廃油 | 水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設において生じたもの | 対象となる廃溶剤 | |
| 汚泥 廃酸 廃アルカリ | 水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの | 環境省令で定める基準を超えているもの | |
以上のとおり、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物が定められており、それぞれの収集運搬について個別の許可が必要です。
事業活動で発生した廃棄物で、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物にあてはまらない廃棄物については「事業系一般廃棄物」となり、これについても別個の許可が必要ですが、許可の取得要件が厳格で、新規参入者の許可取得見込みが低いことから、ここでは説明を割愛します。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可取得の基準について
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可を取得するには、以下の基準を満たしている必要があります。
施設についての基準
ア 運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること。
イ 産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
申請者の能力についての基準
ア 産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
この基準を満たしていることを証明する書類として、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証が必要となります。
そのため、申請者は、許可申請の前に、この講習会を受講しておく必要があります。
イ 産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要です。許可申請に際して、決算書類等を提出し、審査を受けます。
ウ 欠格要件に該当していないこと。
申請者、法定代理人、役員、使用人、株主などが欠格要件に該当していると、不許可となります。
欠格要件は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号や、同法7条第5項第4号に、次のとおり定められています。 細かい規定ですので、一部のみ抜粋します。
(参考)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項(抜粋)
5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者※
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
※(参考)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号(一部抜粋)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ~ト (略)
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可後の手続き
以上の許可基準を満たし、許可を取得した後には、次のような手続きがあります。
許可の更新・変更
産業廃棄物に係る業の許可については、5年ごとに更新許可を受ける必要があります。
取り扱う品目の追加など、事業の範囲を変更しようとする場合は、あらためて許可を受ける必要があります。
変更届・廃止届・欠格事項該当届
許可の取得後に、許可申請時に届け出た事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
事業を廃止した場合には、廃止届の提出が必要です。
申請者や役員等が欠格要件に該当したときは、その届出が必要です。