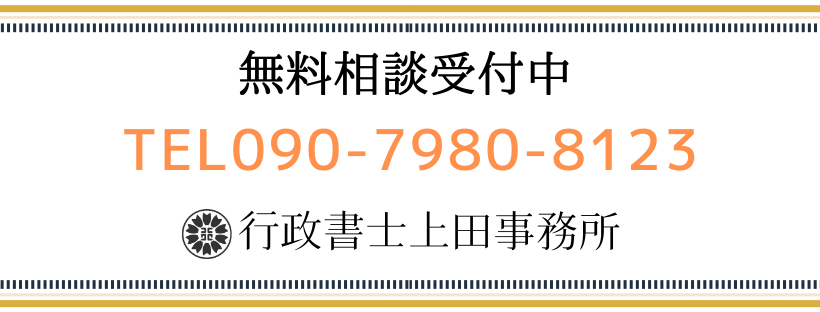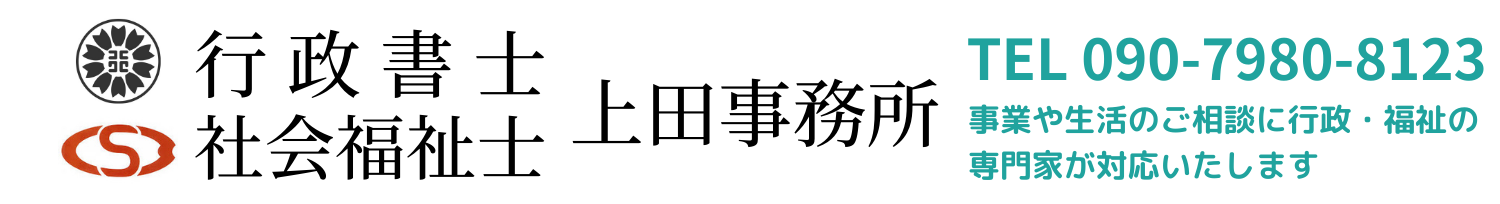東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県で、建設業許可の取得を考えておられる建設業者の皆様に、ご提案いたします。
建設業許可を取得するメリットには、次のようなものがあるといわれています。
大きな契約金額の工事を請け負えるようになります。
建築一式工事は1,500万円以上、その他の工事業種は500万円以上の工事を請け負えるようになります。
公共工事を受注する第一歩になります。
※公共工事を受注するには、許可取得後、さらに別途の審査を受ける必要があります。
許可取得によって、社会的信用を得られます。
許可を取得できるほどの実績があり、法令を遵守している建設業者として信用を得られます。
料金表
建設業許可に関する申請・届出等につきまして、弊所の報酬額は次のとおりです。
以下の料金は、すべて都道府県知事から一般建設業許可を取得する場合のものです。
| 申請・届出の種類 | 金額 |
| 建設業許可新規申請 | 100,000円から |
| 建設業許可更新申請 | 50,000円から |
| 業種追加 | 50,000円から |
| 事業承継 | 100,000円から |
| 経営事項審査・経営状況分析 | 80,000円から |
| 入札参加資格審査 | 30,000円から |
| 全省庁統一資格審査 | 50,000円から |
| 事業年度終了届・決算変更届 | 20,000円から |
| 経営業務の管理責任者の変更届 | 20,000円から |
| 専任技術者の変更届 | 20,000円から |
| 役員等の変更届 | 20,000円から |
| 営業所の住所の変更届 | 20,000円から |
| 廃業届 | 20,000円 |
| 申請等に伴う定款作成 | 20,000円 |
※次の申請等は、上記の料金のほかに、申請手数料等を都道府県に支払う必要があります。
・新規申請(一般建設業許可・都道府県知事) 90,000円
・更新申請(一般建設業許可・都道府県知事) 50,000円
・経営事項審査 審査対象となる業種の数により、11,000円から
・経営状況分析 12,500円
※別途、諸経費(交通費・郵送料・公共機関の文書発行手数料)等が発生いたします。
※それぞれの申請・届出の内容につきましては、このページ内で、個別にお見積額等をご説明しております。目次をご覧いただき、各申請・届出の項をご確認ください。
※特定建設業許可、大臣許可は、別途お見積もりとなります。
行政書士に建設業許可の申請を任せるメリット
行政書士は、建設業者の皆様に代わって、職権で、建設業許可の申請ができます。
(行政書士法第1条の2、第1条の3)
行政書士に任せることで、建設業許可の取得手続きを効率よく進められます。
①ご自身で許可申請を行う場合の時間的損失を回避できます。
弊所に代行させることで、本業に集中していただけます。
②弊所は、東京都江戸川区で営業しております。
関東圏の案件に、迅速丁寧に対応いたします。
③弊所の代表は、元国家公務員であり、行政手続きの専門家・経験者です。
文書作成や資料収集、官公庁との折衝など、丁寧に対応いたします。
④成功報酬制です。万一、許可が取れなかった場合、報酬をいただきません。
なお、現状、申請した案件は、すべて許可を取得しております。
新規申請(新しく建設業許可をとりたい)
都道府県知事の許可を新しく取る場合の一般的なお見積もりは次のとおりです。
弊所の報酬 100,000円から
都道府県に支払う申請手数料 90,000円
諸経費(交通費、郵送料、公文書の取得手数料) 数千円程度
合計200,000円+数千円
なお、以下の場合などに、お見積もりが加算されることがあります。
① 許可を取る工事業種が複数あるとき
② 経営者様や技術者様の経験年数を証明することが必要なとき
③ 会社様が申請する場合に定款を紛失しているとき
④ 会社様の定款が御社の現状を反映していないとき
⑤ 社会保険料の未納状態があるとき
⑥ 個人事業主様が屋号で登録したいとき
⑦ 申請手続きの開始後に、申請書類の作り直しが発生したとき
例 御社役員の交替、会社移転など
許可申請の流れ
- Step1ご相談ください
「許可を取れるのか?」
「申請の手続きには何が必要なのか?」
「すぐに許可が取れない場合、どうしたらいいのか?」
ご相談は、電話・メールで受け付けています。
TEL:090-7980-8123
メール:ueda-y@ueda-y.com
ご相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。 - Step2お申込み・ご契約
ご相談後、お申込みいただいた場合、ご契約書を取り交わし、委任状をいただきます。
ご契約後、弊所が許可申請の代行業務に着手いたします。
ここからはご契約の料金が発生いたします。 - Step3資料のお預かり
許可申請に必要な資料をお預かりいたします。
必要な資料は、会社様(個人事業主様)の実情に応じて様々ですが、おおむね次のようなものです。
・本人確認に関する資料(運転免許証、住民票抄本など)
・実務経験や技能の証明資料(資格者証、工事の契約書や請求書など)
・財務関係の資料(決算書、確定申告書など)
・社会保険関係の資料(保険証、保険料の領収書など) - Step4準備
お預かりした資料をもとに、必要な書類を、弊所が収集・作成いたします。
あわせて、都道府県との協議を経て、不明点を解消していきます。 - Step5申請
都道府県の窓口にて、申請書類を提出いたします。
このとき書面審査があり、この審査を通過した場合、許可を取れる可能性があるといえます。
この書面審査の通過後、申請手数料9万円を支払います。
これで申請書類は、都道府県に受理されたことになり、さらに審査が続きます。審査期間の目安は、申請書類を受理してから、おおむね次のとおりです。
・東京都 25日程度(平日のみ数えて)
・神奈川県 50日程度
・埼玉県 30日程度
・千葉県 45日程度 - Step6許可取得(案件終了)
許可を取れた場合、都道府県から会社様(個人事業主様)あてに、許可通知書が届きます。
許可通知書は、会社様(個人事業主様)が建設業許可を持っていることの証明になる書類です。大切に保管してください。 - Step7【補足】許可取得後の手続き
建設業許可を取った後は、次の手続きがあります。
・許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新が必要です。
・毎年度、決算について届出が必要です。
・登録事項に変更があると届出が必要です。
(例)経営者や技術者が異動したとき、営業所を変更したとき、など
・新たな工事業種の工事を請け負う場合、追加の許可が必要です。
・公共工事を請け負う場合には、そのための審査の手続きが必要です。これらについても、弊所をお使いいただけます。
ご相談いただけますと幸甚でございます。
許可を取れるかどうかのライン
許可を取れるかどうかの大まかなライン
① 建設業の経営者として、5年以上の経験があるか。
(社長、役員、個人事業主など、いわゆる「経営者」の立場にある方のいずれかに、5年以上の経営経験があるかどうか)
② 許可を取りたい工事について、社員(または申請者本人)に工事に関する専門技術があることを、次の方法で証明できるか。
・その工事に関係する国家資格などを持っている
・工業高校や大学の工学部など、工事に関係する学科を卒業している
・その工事について10年以上の経験がある
①と②は、基本的に同一人物でも大丈夫です。
※許可を取るためには、ほかにも必要な条件がありますが、まずは①と②の条件を満たすところからスタートという感じです。
※①と②の条件を満たしていない場合でも、どうしたらいいのか、という相談に対応しております。(相談無料)
令和2年10月1日から、建設業許可を取得した建設業者には、社会保険の加入が義務付けられました。
このため、今後は、これから建設業許可を取得する建設業者の皆様も、申請前に社会保険に入っている必要があります。
社会保険の加入条件と保険の種類
以下のとおり、法人・個人の種類によって加入する社会保険が違います。
法人(株式会社、合同会社、有限会社など)
労働者を1人でも雇っていると、次の社会保険に加入する義務があります。
・雇用保険
・健康保険(協会けんぽ、国民健康保険組合)
・厚生年金
個人事業主
常時使用する労働者の人数によって、次の社会保険に加入する義務があります。
①常時使用する労働者が5人以上
・雇用保険
・健康保険(協会けんぽ、国民健康保険組合)
・厚生年金
②常時使用する労働者が5人未満
・雇用保険
・国民健康保険(国民健康保険組合)
・国民年金
一人親方
・国民健康保険
・国民年金
※社会保険に加入しない場合、以下の不利益があります。
・建設業許可を取得できません。
・すでに許可を取得している建設業者様は、許可を更新できません。
・国や都道府県、元請業者から、加入指導を受けることがあります。
・下請に選定されないことや、現場入場が認められないことがあります。
・建設業許可の監督部局から監督処分を受けることがあります。
令和5年3月現在、江戸川区に営業所を構え、東京都知事から建設業許可を取得している建設業者様の登録状況は、2,648件となっております。
(国土交通省の企業情報検索システム参照)
ちなみに、登録件数の上位3業種は次のとおりです。
第1位 とび・土工・コンクリート工事 755件
第2位 内装仕上工事 544件
第3位 建築一式工事 463件
(いずれも一般建設業です)
江戸川区の数多くの建設業者の皆様が、建設業許可を取得されて、ご活躍されています。
まだ許可を取得されていない建設業者の皆様につきましても、許可を取得されることで、益々のご発展を遂げられることをご期待申し上げます。
建設業許可を取得したあとの手続き
都道府県の建設業許可を取った事業者様につきまして、その後の各種手続きのお見積もりは、おおむね次のとおりです。
決算の届出
建設業許可を取った事業者様は、毎年度、都道府県に、決算を報告する必要があります。
毎年度の決算の届出(都道府県によって「決算変更届」「事業年度終了届」などといいます)
報酬 1年度につき20,000円から
諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など) 1,000円程度
合計 20,000円+1,000円程度
※経営事項審査をともなう事業者様の届出は、別途のお見積もりとなります。
申請内容の変更の届出
建設業許可を取得したときの申請内容に、後日、変更が生じた場合は、届け出る必要があります。
申請内容の変更の届出
(商号・屋号、所在地、電話番号、代表者、技術者、役員、技術者の変更、営業所の追加など)
報酬 20,000円から
諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など) 1,000円程度
合計 20,000円+1,000円程度
※届出事項が多岐にわたる場合、別途のお見積もりとなります。
※技術者の変更、営業所の追加の届出は、別途のお見積もりとなります。
建設業許可の更新
建設業許可は5年ごとの更新制です。
更新時には申請が必要です。
申請の流れは、新規申請時と同じです。
建設業許可の更新
報酬 50,000円から
申請手数料 50,000円
諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など) 数千円程度
合計 100,000円+数千円程度
なお、以下の場合などに、お見積もりが加算されることがあります。
① 許可の更新期限まで時間が無いとき(案件をお断りする場合もございます)
② 更新する工事業種が複数あるとき
③ 経営者様や技術者様の交替があるとき
④ 会社様が申請する場合に定款を紛失しているとき
⑤ 会社様の定款が御社の現状を反映していないとき
⑥ 社会保険料の未納状態があるとき
⑦ 決算の届出など、これまでに届け出る書類を届け出ていないとき
⑧ 申請手続きの開始後に、申請書類の作り直しが発生したとき
例 御社役員の交替、会社移転など
工事業種の追加
すでに許可を取得している事業者様が、さらに別の工事業種で大きな工事を施工することになり、その工事業種の許可を取得する場合、業種追加の申請が必要です。
建設業許可の業種追加
報酬 1業種50,000円から
申請手数料 50,000円
諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など) 数千円程度
合計 100,000円から+数千円程度
なお、以下の場合などに、お見積もりが加算されることがあります。
① 許可の更新期限まで時間が無いとき(案件をお断りする場合もございます)
② 更新する工事業種が複数あるとき
③ 経営者様や技術者様の交替があるとき
④ 会社様が申請する場合に定款を紛失しているとき
⑤ 会社様の定款が御社の現状を反映していないとき
⑥ 社会保険料の未納状態があるとき
⑦ 決算の届出など、これまでに届け出る書類を届け出ていないとき
⑧ 申請手続きの開始後に、申請書類の作り直しが発生したとき
例 御社役員の交替、株式譲渡、会社移転など
廃業したとき
建設業許可の有効期間中に、建設業を廃業するときは、廃業届が必要です。
廃業の届出
報酬 20,000円
諸経費(郵送料、交通費など) 1,000円程度
合計 20,000円+1,000円程度
なお、以下の場合などに、お見積もりが加算されることがあります。
① 決算の届出など、これまでに届け出る書類を届け出ていないとき
② 届出手続きの開始後に、書類の作り直しが発生したとき
例 御社役員の交替、会社移転など
地方自治体の公共工事の入札に参加したい
建設業許可を取得した事業者様は、手続きを踏むことで、公共工事の入札に参加できます。
入札参加のルールは、入札を実施する地方自治体ごとに個別のルールがあり、さらに入札ごとにも個別のルールがありますが、少なくとも、次の2つの手続きが必要です。
・経営事項審査を受審する
・入札を実施する地方自治体の入札参加資格を取る
以下、それらについての一般的なお見積もりとなります。
経営事項審査
公共工事の入札は、その公共性の高さから、信用のある事業者だけが参加できます。
あらかじめ、入札を実施する地方自治体の審査を受ける必要があり、これを経営事項審査といいます。
経営事項審査では、さまざまな項目(財務状況が安定しているか、施工技術があるか等)の審査を受けます。なお、毎年入札に参加し続けるためには、この審査を毎年受審する必要があります。
経営事項審査(経営状況分析を含む)
報酬 80,000円から
申請手数料 10,000円(工事業種を1つ追加ごとに2,500円加算)
諸経費(経営状況分析手数料、郵送料、交通費、公文書発行手数料) 2万円程度
合計 130,000円から
※別途、審査対象年度の決算の届出も承ることを想定したお見積もりです。
なお、以下の場合などに、お見積もりが加算されることがあります。
① 期日が切迫している場合(案件をお断りする場合もございます)
② はじめて経営事項審査を受けるとき
③ 工事業種が複数あるとき
④ 工事実績に単価契約が含まれているとき
⑤ 決算の届出など、これまでに届け出る書類を届け出ていないとき
⑥ 申請手続きの開始後に、申請書類の作り直しが発生したとき
例 御社役員の交替、会社移転など
入札参加資格審査申請
経営事項審査の終了後、その審査結果をもとに、経営事項審査を受審した都道府県内にある地方自治体に対して、入札参加資格の取得申請をします。
入札参加資格申請
報酬 1か所30,000円から
諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など) 数千円
合計 30,000円から
※別途、審査対象年度の経営事項審査も承ることを想定したお見積もりです。
なお、以下の場合などに、お見積もりが加算されることがあります。
① 期日が切迫している場合(案件をお断りする場合もございます)
② はじめて経営事項審査を受けたとき
③ はじめて入札に参加しようとする地方自治体に申請するとき
④ 工事業種が複数あるとき
⑤ 工事実績に単価契約が含まれているとき
⑥ 決算の届出など、これまでに届け出る書類を届け出ていないとき
⑦ 申請手続きの開始後に、申請書類の作り直しが発生したとき
例 御社役員の交替、会社移転など
国(政府)の入札に参加したい
政府の出先機関(財務局、運輸局、法務局など)も入札を行っています。
入札に参加するためには、全省庁統一資格審査を受け、参加資格を取る必要があります。
全省庁統一資格審査申請
報酬 50,000円から
諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など) 数千円
合計 50,000円から
その他のお見積もり
以下のご依頼は、ご相談に応じて、別途のお見積もりとなります。
・特定建設業に関する許可申請
・国土交通大臣に対する許可申請
弊所について
| 事務所名 | 行政書士 上田事務所 |
| 代表者 | 行政書士 上田 雄也(うえだ ゆうや) |
| 所属 | 東京都行政書士会 |
| 所在地 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西4-3-5-207 |
| TEL | 090-7980-8123 03-4500-8200 |
| FAX | 03-6332-9123 |
| 営業時間 | 9:30~20:00 |
| 対応地域 | 東京、神奈川、埼玉、千葉(その他の地域も応相談) |
代表あいさつ
弊所のご提案を最後までご覧いただき、ありがとうございます。
弊所の代表を務めます行政書士の上田雄也と申します。
当職は、国家公務員として、法務省などで14年間ほど勤務しておりましたが、その経験を通じて、より社会に貢献したいとの思いが募り、一念発起して公務員を退官し、2019年3月に独立し、行政手続きの専門家として行政書士を開業いたしました。
開業にあたっては行政書士という資格も必要でしたし、やっていこうという決心も必要でした。
こうした自身の経験から、これから建設業許可を取り、事業をより発展させていこうと歩みだした事業者様を応援させていただけたらと思い、建設業許可の申請のお手伝いをしております。
また、公務員であったころは、小規模な公共工事等の入札・見積合わせの担当をしたこともありました。その当時は、公共工事等の発注者としての立場でしたので、すでに建設業許可を取得している事業者様が交渉相手であり、まだ許可を取得していない、もしくは許可を必要とするような大きな工事をなさらない事業者様とのお付き合いは、ほとんどありませんでした。このため、建設業許可の取得について、事業者様のお悩みをうかがい知る機会もございませんでした。
他方、行政書士になってからは、これから建設業許可をとってご活躍になる事業者様とのお付き合いがほとんどです。現在、建設業界におけるコンプライアンスの高まりとともに、信頼の証として建設業許可を必要とする機会が増えているといわれています。そのため、そもそも許可を必要とするような大きな工事をするつもりのなかった事業者様についても、どうにかして許可を取りたい、とのご要望をいただくことが増えています。こうした事業者様について許可取得をサポートし、ゆくゆくは公共入札にも参加できるような事業者様になるべくサポートを続けていくことができたらと思っております。
以上、雑感を申し述べました。
当職は、行政書士としては、まだ開業4年目と、駆け出しも同然でございます。大きく構えず、慢心せず、ひとつひとつの仕事や出会いを大切にしていきたいとの思いがございます。
このたびのご提案によりまして、建設業者の皆様のお力になれれば、誠に幸甚でございます。
皆様が、建設業許可を取得され、益々のご発展を遂げられることを祈念しております。
参考記事
以下の記事で、建設業許可について簡単にまとめました。
許可手続きについて、もっと知りたい方や、ご自身で許可申請に挑戦してみたい方は、ご一読ください。