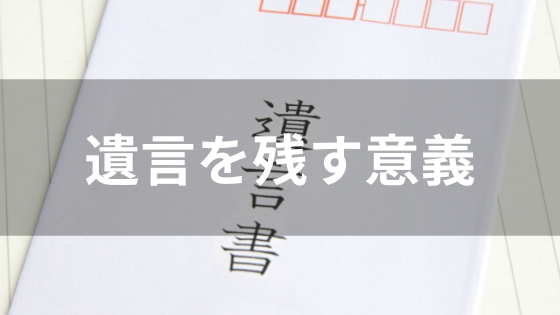遺言は、残しても残さなくても、構わないものです。残さない人も、たくさんいます。
この点、遺言を残したほうがいい場合があるのでしょうか。
また、遺言は、どのような形でも、残しさえすれば、それが遺言になるのでしょうか。
遺言の意義や、遺言を残したほうがいいケース、遺言の基本となる法律を説明します。
遺言を残すべきか考えている方や、遺言の基本について知りたい方のための記事です。
遺言とは
遺言とは、自分が生涯をかけて築いてきた永年の努力の所産を、親族などに、自分の思うとおりに引き継がせ、その親族などの人生に役立たせようとする意思表示といえます。
また、そうした引き継ぎの背景にある自分の真意を親族などに伝えるものともいえるでしょう。
この点、世の中には、遺言を残さない方も少なくありません。
遺言を残すか否かは、遺言をする人(以下「遺言者」といいます) の自由であるからです。
しかしながら、遺言を残したほうがいい場合があるともいわれています。
遺言を残すメリット
遺言を残すメリットは、遺言者が亡くなった後のトラブル防止にあります。
遺産相続において、遺言者が次のことを考えている場合には、遺言者が遺言によってハッキリと意思表示をしておかないと、遺言者の死亡によって、トラブルが生じやすいといわれています。
・ある相続人に、法で定められた割合以上の遺産を与えるとき
・ある相続人を遺産相続から除外するとき
・ある相続人に家を、また別の相続人に現金を、と種類が異なる遺産を分け与えるとき
・相続人になれない人(内縁の妻、息子の妻など)に遺産を与えるとき
・認知したい子どもがいて、遺言で認知するとき
このような場合は、遺言者の意思が強く反映された遺産相続となるので、相続人にとっては想定外の事態になりがちです。
遺言者は、遺言を残して明確に意思表示しておくことで、遺産相続に関するトラブルを防止できる可能性があります。
遺言のルールについて
遺言は、遺言者にとって、人生の最後のメッセージともいえるものです。
その性質から、遺言に関することは、遺言者の自由意思で決められることが望ましいといえます。
遺言を、どのような形式で残すのか、文章にするのか、録音にするのか、それとも、いま流行の動画にするのか、あるいは、信頼できる親族に伝言しておくのか、すべて自由であってもいいはずです。
遺言の内容についても、何をどうしようと、すべて自由であってもいいはずです。
しかしながら、わが国では、遺言について「民法」という法律でルールを定めています。
民法における遺言について
民法という法律は、私たちの日常生活について、多種多様なルールを定めており、世の中に数ある法律の中でも、基本的な法律のひとつであるといえます。
民法は、遺言について、次のとおり定めています。
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
出典:民法第960条(遺言の方式)
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。(略)
出典:民法第967条(普通の方式による遺言の種類)
民法は、遺言を「証書」によってすることを原則としています。
つまり、遺言は、証拠になることを意識して、しっかりと書かなければいけないということです。
一般的に”遺言書”といわれるものです。
もし、この定めを知らなかったことで、録音や動画など “民法に定める方式に従わない遺言”を残してしまった場合、残念なことに、その遺言は無効ということになってしまいます。
遺言が無効になることで、遺言者が望まない結果になったとしても、やむを得ない、ということになります。
どうして、あえて法律で、このように定めているのでしょうか。
世の中では、遺言がなされたものの、その形式や内容が不適切であったために、遺言の存在や解釈をめぐって、相続人の間で争いが起こることが少なくありません。
遺言者にとって、自らのしたことで、残された親族が争うことほど、残念なことはないでしょう。
そこで、わが国では、民法によって、遺言のルールについて定めることで、”骨肉の争い”の予防の一助としているのです。
また、遺言書を書くにしても、メモ書きのような曖昧な遺言書では、トラブルの原因となる不明確な遺言となりかねないので、証書という形で、しっかりした遺言書を残すことを定めています。
加えて、遺言書は、その作者である遺言者が死亡した後に用いるものであるため、遺言書が偽造や変造された場合に、遺言者によって是正することができません。
そのため、民法では、偽造や変造の対策のためにも、厳格なルールを定めています。
この民法が定める遺言のルールについて、よく理解することが、適切な遺言を残すことにおいて重要であるといえるでしょう。
上記の民法第960条や第967条を見てのとおり、民法の定めを知らずに遺言を残してしまったら、取り返しのつかないことになってしまいます。
さらに、同条にいう「この法律に定める方式」についても、民法にいろいろと定められているので、知っておく必要があります。
この点、いざ決心し、遺言書をしたためる気持ちにはなったものの、何をどう書くべきか決めかねて筆が進まない場合や、ある程度は形になったものの下書きから進まない場合、書けはしたものの適切な遺言書であるのか判断がつかない場合などは、遺言書が未完成のまま、貴重な時間だけが過ぎていってしまいます。
このような場合、行政書士などの専門家を活用することについて検討の余地があります。
まとめ
遺言は、相続のトラブルを意識して、明確な意思表示をすることで、相続争いを防止する効果を期待できます。
遺言は、民法に定める方式に従って書くことで、有効な遺言として認められます。